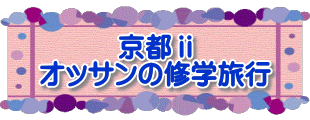|
 |
| 2015年3月10日撮影 地下鉄「二条城前駅」です.駅構内のスペースがゆったりとした感じです.また,ホームの安全扉があって安心です. |
2015年3月10日撮影 駅には傘の自動販売機がありました.関東でもあるのでしょうか?見たことがありませんが. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 地下鉄の駅の地上に出て,横断歩道を渡ると直ぐに「二条城」が見えてきました.この時は,「東大手門(修理中)」が出入り口となっていました.「東大手門」が工事中だったので少し残念でした. 上の写真は「東南隅櫓」を中心に見た「二条城」の外堀です.この「二条城」の石垣はとても品格があり,眺めていても飽きません. この「二条城」は,慶長8年(1603年),徳川初代将軍家康が京都御所の守護と将軍上洛の際の宿泊所として造営し,三代将軍家光が,伏見城の遺構を移すなどして,寛永3年(1626年)に完成したものです.従って,家康が建てた慶長年間の建築と家光がつくらせた絵画・彫刻などが統合した,所謂桃山文化の全貌を見ることができます.慶応3年(1867年)十五代将軍慶喜の大政奉還により,二条城は朝廷のものとなり,明治17年(1884年)には離宮,昭和14年(1939年)京都市に下賜されました.平成15年(2003年)には築城400年を迎えました.(入場券記載の説明文より) |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 お堀に沿って入り口に向かって歩いて行くと,この石碑がありました. 「二条城」は1994年に世界文化遺産に登録されました. |
2015年3月10日撮影 この少し先の右側に「唐門」があります. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 東大手門から入り,「唐門」へ.この「唐門」は「二の丸御殿」の正門で,寛永2年(1625年)に後水尾天皇の行幸を迎える工事の一環で建てられたものです.虹梁や貫上には牡丹唐獅子などの豪華な彫刻が施されています. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「唐門」は「二条城」の威厳を感じさせます.どの角度から見ても美しいです. |
2015年3月10日撮影 「二の丸御殿」の玄関である「車寄」は華麗な装飾で彩られ,鶴や牡丹など,欄間には裏と表で異なる彫刻が施されています.左手奥には参内した大名が控える場所である「遠侍(とおざむらい)」があります. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「二の丸庭園」の入り口に鐘が二つ? この鐘は二条城と京都所司代との連絡用に使われた鐘とのことです. |
2015年3月10日撮影 「二の丸御殿」の「遠侍」の外観.建物の側面の造りに威厳を感じます. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「二の丸御殿」の大広間. この「大広間」は将軍が外様大名と謁見した重要な任務を行っていた場所であり,「二の丸御殿」の中でも最も格式の高い部屋とされています. |
2015年3月10日撮影 火災除けのおまじないともいえる「懸魚」の部分の造りも,かなり手が込んでいます. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 写真の奥から順に「遠侍」,「式台」,「大広間」です.何故かジグザグになっています.「二の丸御殿」の総面積は3300㎡もあり,部屋は全部で33,そして800枚もの畳が敷かれているそうです.せっかくの熱いお茶も運ぶ間に冷めてしまいそうです. |
2015年3月10日撮影 瓦,特にエッジの部分にも美を意識した造りとなっています. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 こうして写真だけを見ると観光客が写っていませんが,実際には修学旅行の団体も含め,かなりの観光客がいました. 何処からか琴の音が聞こえてきそうな,落ち着きを感じさせる「二の丸庭園」です. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「二の丸庭園」に関する駒札の説明文を転記します. 池を中心とした書院造庭園であり,庭には三つの島を置き,四つの橋を架け,西北隅には滝を落とし,池の汀に多くの岩石を配した景観は,変化に富んで秀麗であり,豪壮な趣がある.庭園は大広間の西,黒書院の南に位置し,主として大広間からの鑑賞を想定して造られているが,寛永3年の後水尾天皇行幸の際,行幸御殿が庭園の南側に建造されたことから,南方からの鑑賞も考慮して,庭園南部の石組に変化をくわえた形跡が見られる.作庭年代については,記録や作風から推察して,1603年(慶長8年)の二条城築城の際に,その建築に調和させて造営されたもので,後水尾天皇の行幸の際に,数多くの名園を手がけた小堀遠州によって一部改修が加えられ,今日に至ったものと考えられる.桃山時代末期から江戸初期に大成された書院造の大建築に伴う庭園の特徴をよく示しており,現存する歴史的庭園の中でも最も優れた作品の一つに数えられている. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 左に「桃山門(写真左)」,右に「鳴子門(写真右)」を見ながら「本丸御殿」の入り口へ. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 お堀(内堀)を渡り,「本丸櫓門(写真右)」をくぐって,「本丸御殿」エリアに入ります. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 これは明治時代に造園された「本丸庭園」です. |
2015年3月10日撮影 「天守閣跡」より「本丸御殿」を望む. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「天守閣跡」より,南側の内堀を望む.所々に「ウメ」が咲いています. 以下,天守閣跡の駒札より転記しました. 二条城の天守閣は,寛永3年(1626年)に伏見城から移築されたもので五層の天守が建てられていましたが,寛延3年(1750年)に落雷により焼失し,再建されることなく現在に至っている.現存する天守台は高さ21m,天守台の敷地445㎡あります. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「本丸御殿」の玄関です.「唐門」と違ってかなり地味な印象です. |
2015年3月10日撮影 「本丸御殿」エリアから西側への出口です.ここの石垣もかなり高度な技術で造られていると思います. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「本丸御殿」を出て西側へ向かう内堀です. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 妙にくねくねとした木です.この辺りは枝垂桜が多く,その時期はライトアップされ,さぞ見事でしょうね・・・その反面,観光客も多いと思いますが. |
2015年3月10日撮影 南側通路より,天守閣跡を見上げます. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 この辺り一帯は約130本の「ウメ」が咲き誇る,梅園になっています. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「ロウバイ」も咲いていました. |
2015年3月10日撮影 内堀と「本丸御殿櫓門」を望む. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「桃山門」の入り口を通過し,「二条城」の出口へと向かいます.モデルコースは「本丸御殿」を出た後,北へ廻るようですが,今回は南側へ出てしまいました. |
2015年3月10日撮影 「二条城」のお堀を背にし,バス停(二条城前)へ移動し,一路「金閣寺」へ.この移動中,雪が最も激しくなってきました.「二条城」を観光中には,それほど雪も降らずラッキーでした. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「金閣寺(通称)・鹿苑寺」に到着しました.まだ時折雪が舞い,とても寒かったです.積もるような雪であれば,それはまた違った美しさの「金閣寺」が拝めるかも? と淡い期待を抱きながら・・・. |
2015年3月10日撮影 この「金閣寺」も1994年に世界遺産に登録されました. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 入り口まで,もう少し歩きます.皆さん防寒対策がばっちりです. |
2015年3月10日撮影 「舟形石」.一体何のために? |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 1492~1504年に建てられたとみられる「庫裏」.入り口(受付)の少し手前にあります. |
2015年3月10日撮影 入り口(受付)近くにある「イチイガシ」の老木.樹齢は分かりません. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 確か受付のある建物の瓦だと思いますが,獅子が乗っています. |
2015年3月10日撮影 「金閣寺」・・・「鏡湖池」の向こうに金色に輝く「「舎利殿」.何とも言葉では表現できません. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 以下,「金閣寺」のパンフレットより転記します. お釈迦様の舎利(お骨)をまつった舎利殿「金閣」が特に知られ「金閣寺」とよばれていますが,正しくは「鹿苑寺」と言い,臨済宗相国寺派の禅寺です.この地は,鎌倉時代に西園寺公経の別荘「北山第」が在りましたが,足利三代将軍義満が気に入り,応永4年(1397年)に西園寺家から譲り受け,山荘「北山殿」を造りました.「金閣」を中心とした庭園・建築は極楽浄土をこの世に現したと言われ,後小松天皇(一休禅師の父)をお招きしたりしました.室町幕府は中国(明国)との交易を盛んに行い,北山文化の中心地として発展しました.義満没後,遺言により夢窓国師を開山(初代の住職)とし義満の法号鹿苑院殿から二文字をとり,「鹿苑寺」と名付けられました. 1994年,世界文化遺産に登録されました. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 昭和25年(1950年)7月2日未明,放火により国宝の舎利殿(金閣)と安置されていた仏像等を焼失(金閣寺放火事件).昭和27年(1952年)着工,昭和30年(1955年)竣工,創建当時の姿に復元されました. この金閣寺の火災については三島由紀夫「金閣寺」の題材にもなりました. |
2015年3月10日撮影 以下,金閣寺のパンフレットより抜粋しました. 金閣の2層と3層は漆の上から純金の箔が張ってあり,屋根は椹の薄い板を何枚も重ねたこけら葺で,上には中国でめでたい鳥といわれる鳳凰が輝いています.1層は寝殿造で法水院,2層は武家造で潮音洞,3層は中国風の禅宗仏殿造で究竟頂とよばれ,三つの様式を見事に調和させた室町時代の代表的な建物です. ※使われた金箔の総重量は20kgだそうです. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 立札には, 「銀河泉」・・・「義満公 御茶ノ水」とありました.きっと,この水を使ってお茶をたてたのでしょう. |
2015年3月10日撮影 立札には, 「厳下水」・・・「義満公お手洗いの水」とありました. ん~何のときに手を洗ったのでしょうか? |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 小高い所から「舎利殿」を望む. |
|
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 滝とその滝を登ろうとする鯉に見立てた石から「龍門瀧」と「鯉魚石」と呼ばれているそうです. |
2015年3月10日撮影 立札には, 「貴人榻(きじんとう)」・・・「昔,高貴な人が座られた腰掛石.室町幕府によって移設された. とあります. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「夕佳亭」.後水尾天皇を迎える際,住職の鳳林承章が茶人の金森宗和に造らせたという数寄屋造りの茶室.「夕佳亭(せっかてい)」の名前には夕日に映える金閣寺が佳(よ)いという意味が込められている. |
2015年3月10日撮影 立札には, 「足利八代将軍義政公 遺愛 富士形 手水鉢」とあります. |
 |
 |
| 2015年3月10日撮影 「不動堂」.かなり多くの方がお詣りをしていました. 以下,パンフレットより転記します. 「不動堂」に祀られる本尊は弘法大師が作られたと伝えられる石不動明王で,霊験あらたかな秘仏として広く一般に信仰されています.節分と8月16日に開扉法要がいとなまれます. |
2015年3月10日撮影 「金閣寺」を後にして,「銀閣寺」へ向かいます. |
| かなりハードな京都世界遺産巡りの旅二日目ですが,未だ半分です.これから銀閣寺へ移動し,その後は清水寺です.かなり,足にきています.二日目の後半は次のページ「京都ⅲ」です. | |