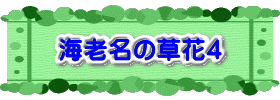
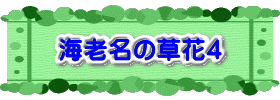
 |
 |
| 2015年7月2日撮影 「ハス」の開花は,もう少しですね. |
2015年7月2日撮影 散歩道に咲く「フヨウ」です. |
 |
 |
| 2015年7月7日撮影 花が開きかけてきました. |
2015年7月7日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月7日撮影 | 2015年7月7日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月8日撮影 | 2015年7月8日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月8日撮影 「ハナシキブ」の蜜を吸う「ダンゴバチ」.「ダンゴバチ」の重さで撓っています. |
2015年7月10日撮影 「ヤブガラシ」と「モンシロチョウ」. |
 |
 |
| 2015年7月11日撮影 「ハス」の花びらに陽が当たり,透けているところが綺麗です. |
2015年7月11日撮影 この草花の名前が分かりません.「海老名の野草1」の2015年2月15日の写真と似ていると思うのですが・・・. |
 |
 |
| 2015年7月11日撮影 「子育て支援センター」近くの用水路のブロックに咲いていた「マルバハギ」.葉の形が丸いのが特徴です. |
2015年7月12日撮影 「ノアザミ」. |
 |
 |
| 2015年7月12日撮影 | 2015年7月12日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月12日撮影 | 2015年7月12日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月12日撮影 | 2015年7月14日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月14日撮影 | 2015年7月14日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月14日撮影 | 2015年7月17日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月17日撮影 | 2015年7月22日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月23日撮影 田圃の畦道で見掛けた「ミゾカクシ」です.溝を隠すほど茂るので“溝隠し”と名付けられたとのこと・・・でも,最近はあまり見掛けなくなったのではないでしょうか. |
2015年7月25日撮影 花托が成長してくると,もう少しで花は終わりを迎えます. |
 |
 |
| 2015年7月25日撮影 | 2015年7月27日撮影 |
 |
 |
| 2015年7月29日撮影 貫抜川の土手に咲く,「イヌゴマ」.「ゴマ」に似ているが,食べられないことから“役に立たない”ことを意味し,“犬胡麻”になったようです.でも“犬”=“役に立たない”は疑問です.葉や茎にトゲがあり,嫌われ者の雑草です. |
2015年7月30日撮影 |
 |
 |
| 2015年8月1日撮影 | 2015年8月1日撮影 |
 |
 |
| 2015年8月11日撮影 貫抜川の土手に咲く「フヨウ」です.完全に野生化しています. |
2015年8月12日撮影 貫抜川の土手にはたくさんの「クコ」の木があり,このように小さな紫色の花を咲かせます.中国が原産地の外来種で,食用や薬用に利用されています. |
 |
 |
| 2015年8月12日撮影 貫抜川の散歩道に咲く「オシロイバナ」.このように「オシロイバナ」も野生化しています. |
22015年8月13日撮影 赤くなる前の「カラスウリ」です.やはり「ウリ」なのか,縞模様があります. |
 |
 |
| 2015年8月13日撮影 「ハス」が実になっていました.全体が蜂の巣,そして種子が蜂のサナギのように見えます. |
|
 |
 |
| 2015年8月13日撮影 「フヨウ」に止まる「チャバネセセリ」. |
2015年8月14日撮影 真夏なのに「フジ」が咲いています.市役所から海老名駅に向かう歩道の藤棚です. |
 |
 |
| 2015年8月20日撮影 田圃に咲く「オモダカ」.稲にとっては邪魔な雑草だと思います. |
2015年8月31日撮影 この「アレチマツヨイグサ」も,空き地のあちこちに咲いています.北米原産の帰化植物で明治時代に野生化したようです. |
 |
 |
| 2015年8月31日撮影 「ママコノシリヌグイ」.茎にトゲがあり,嫌われ者の雑草です.子供のころ,河原を歩いていて,足が赤くなりました.それにしても強烈な名前です.変更した方が良いと思います. |
2015年8月31日撮影 散歩道(海老名消防署の南西辺り)の「カリン」.大きな実がなっています. |
 |
 |
| 2015年8月31日撮影 散歩道の緑の雑草の中でもひと際目立つ「マルバルコウソウ」.原産地は中央アメリカで江戸時代に観賞用として渡来しました. |
2015年8月31日撮影 葉や花の色・形状から「ヒュウガミズキ」だと思うのですが,何故に今頃咲いているのか? |
 |
 |
| 2015年8月31日撮影 田圃の中の「オモダカ」の花(写真左)と花に止まる「ヤマトシジミ」.写真右は「オモダカ」の実です. |
|
 |
 |
| 2015年9月4日撮影 田圃の端に咲く,水田の雑草の仲間.「チョウジタデ」. |
2015年9月4日撮影 こちらも水田の雑草で,写真左の花の横に咲いていた「ホソバヒメミソハギ」です.北アメリカ原産の帰化植物です. |
 |
 |
| 2015年9月4日撮影 同じく水田の雑草(水生植物)の「コナギ」です.稲にとっては邪魔者です.原産地は東南アジアで,水稲耕作と共に伝わったようです. |
2015年9月4日撮影 またまた,水田の雑草「タカサブロウ」.南米原産の帰化植物です. |
 |
 |
| 2015年9月5日撮影 貫抜川沿いの散歩道に咲く「ヤブツルアズキ」. |
2015年9月5日撮影 貫抜川沿いの散歩道に「マンジュシャゲ」が咲き始めました. |
 |
 |
| 2015年9月5日撮影 貫抜川沿いの散歩道にて「マツバギク」の蜜を吸う「チャバネセセリ」. |
|
 |
 |
| 2015年9月7日撮影 「水と花と緑のこみち」の「ハギ」もかなり咲きだしました. |
|
 |
 |
| 2015年9月7日撮影 貫抜川沿いの散歩道の「シロマンジュシャゲ」.少しピンクが混じっています.貫抜川沿いの散歩道の野草を除く草花は,自然に咲いているのではなく,日常から面倒をみてくださっている方がおられるからです.ありがとうございます. |
2015年9月7日撮影 アスファルト道路の道端で見つけた「ショウジョウソウ」(所謂,ド根性です).小さいのですが,この色なのでとても目立ちました.原産地は北アメリカ南部・ブラジル.種子がどこからか飛んできたのでしょうか? |
 |
 |
| 2015年9月7日撮影 「タマスダレ」の蜜を目的に近付いてきたのか? 小さな蜂が飛んできました. |
2015年9月16日撮影 「カラスウリ」が色付いています. |
 |
 |
| 2015年9月16日撮影 貫抜川沿いに咲く「ハナシュクサ」.原産地はインド~マレーシアで,日本へは江戸時代に渡来しました. |
2015年9月20日撮影 貫抜川沿いに咲く「マンジュシャゲ」の蜜を吸う「キアゲハ」・・・メルヘンの世界に飛び込んでしまった感じですね. |
 |
 |
| 2015年9月20日撮影 | 2015年9月20日撮影 |
 |
 |
| 2015年9月22日撮影 | 2015年9月24日撮影 散歩道の「キンモクセイ」.甘い香りが漂います. |
 |
 |
| 2015年9月24日撮影 散歩道で見つけた野生化した「ルコウソウ」.原産国は南アメリカ,江戸時代に渡来したようです.この花の正五角形は自然の芸術だと思います. |
|
 |
 |
| 2015年9月24日撮影 散歩道に咲く「アキノノゲシ」.かなり昔に渡来した帰化植物ですが,完全に日本の雑草になりきっています. |
2015年9月24日撮影 散歩道の葦の茂みの横に咲いていました.恐らく「ハナトラノオ」だと思います.北アメリカ原産で大正時代に日本へ渡来した帰化植物です.しかし,何故このような所に生えているのか疑問が残ります. |
 |
 |
| 2015年9月24日撮影 散歩道の雑草の茂みでは「タマスダレ」がまだ頑張っています. |
2015年9月24日撮影 日本全国で見られる水田の雑草の一つ「イボクサ」.「ツユクサ」の仲間です.紫色のグラデーションが綺麗です. |
 |
 |
| 2015年9月24日撮影 用水路の護岸ブロックに育った「ヤマブドウ」.子供の頃,山で取って食べました.かなり,酸っぱいですが. |
2015年9月28日撮影 「ススキ」が風になびいています. |
 |
 |
| 2015年9月29撮影 散歩道の「クサギ」の実が夕日を浴び,光っていました, |
2015年9月29撮影 「マンジュシャゲ」の花が少なくなり,「キアゲハ」も寂しそうです. |
 |
 |
| 2015年9月29撮影 用水路の護岸に生えている「セイタカアワダチソウ」. |
2015年9月29撮影 「コムラサキ」とそっくりで実が白いだけの「シロミノコムラサキ」です.名前は“まんま”ですね. |
| この「海老名の野草4」は夏の「ハス」に始まりましたが,後半には「マンジュシャゲ」や「ススキ」も登場し,すっかり秋の気配を感じさせてくれました. 8月31日にカメラを担いでブラブラしていた時に,お目にかかった方のことを紹介します. 散歩道にて野草を詳しく観察している女性を見掛けました.声を掛けさせていただいたところ,野草の調査をされているとのことでした(神奈川県より委託され,調査をされていると思います).「ちょっと,この草を見てください」と言われ,普段は単に雑草(シバ)程度にしか思っていなかった野草が実は「神奈川県では希少種」とのことでした.このように地道に調査をされている方がおられるということを,初めて知りました.当然,様々な野草についてとてもお詳しく,またお会いしてお話を伺いたいです. ※この野草は「ウシノシッペイ」と教えていただいた気がしますが,この方が公式に報告されると思いますので,それまでは場所は開示しません. |
|